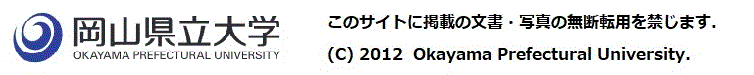
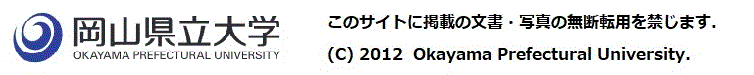
| 授業科目名(和文) [Course] |
論理回路 |
| 授業科目名(英文) [Course] |
Logic Circuits |
| 学部(研究科) [Faculty] |
情報工学部 |
| 学科(専攻) [Department] |
情報システム工学科 |
| 担当教員(○:代表教員) [Principle Instructor(○) and Instructors] |
○横川 智教 自室番号(2504)、電子メール(t-yokoga**cse.oka-pu.ac.jp) ※利用の際は,** を @に置き換えてください |
| 単位数 [Point(Credit)] |
前期 2単位 |
| 対象学生 [Eligible students] |
2年次生 |
| 授業概略と目標 [Course description and Objects] |
論理回路は,コンピュータ内部での電気信号処理によって実現されるディジタル回路を,0と1の二値上の計算へと抽象化することで数学的にモデル化したものであり,現在のマイクロプロセッサを実現するためのディジタル技術の基礎理論となっている. 本講義では,論理回路について学ぶための基礎となる離散数学について概説した上で,論理関数としての表現法について述べ,論理関数の標準形やその最適化手法など論理回路を設計する上での基礎的な理論について講述する.さらに,論理回路の基本構造である組合せ回路と順序回路の構成・動作・特性について実例とともに述べる.また,現在のディジタル回路設計で主流となっているFPGAへの回路実装についても紹介する. |
| 到達目標 [Learning Goal] |
1.論理関数の表現法・最適化手法を理解する. 2.組合せ回路の構成・特性を理解する. 3.順序回路の構成・特性を理解する. 4.ハードウェア記述言語による論理設計技術を理解する. |
| 履修上の注意 [Notes] |
「計算機工学入門」および「離散数学」を履修し,コンピュータのハードウェアや集合論・論理学に関する基礎的な知識を習得しておくことが望ましい. |
| 授業計画とスケジュール [Course schedule] |
1.数学的基礎:集合と論理,二値データ表現 2.論理関数1:ブール代数,二値論理関数 3.論理関数2:論理関数の表現法,真理値表,積・和標準形,二分決定グラフ 4.論理関数3:論理関数の最適化手法,カルノー図,クワイン・マクラスキー法 5.組合せ回路1:組合せ回路の構成,回路図の記法,加算器 6.組合せ回路2:減算器,比較器,エンコーダ,デコーダ 7.組合せ回路3:マルチプレクサ,デマルチプレクサ 8.中間試験 9.順序回路1:順序回路の構成,フリップフロップ 10.順序回路2:順序回路の設計,状態遷移表 11.順序回路3:レジスタ回路,カウンタ回路 12.順序回路4:順序回路の最適化,有限状態機械,ムーア型状態機械,ミーリー型状態機械 13.論理設計1:FPGA,ハードウェア記述言語による設計 14.論理設計2:Verilog HDLとVHDL 15.論理設計3:設計の抽象度,振る舞いレベル設計,レジスタ転送レベル設計,ゲートレベル設計 16.期末試験 |
| 成績評価方法と基準 [Grading policy (Evaluation)] |
中間試験および期末試験によって成績の評価を行う.評価の配分は中間試験50%,期末試験50%とする.なお,その時点における出席率が2/3未満であった場合,中間試験および期末試験の受験は認めない. |
| 教科書 [Textbook] |
教科書:「論理回路入門(第3版)」浜辺隆二(著)(森北出版) 参考書:「電子情報通信レクチャーシリーズ B-5 論理回路」安浦寛人(著),電子情報通信学会(編)(コロナ社) 「New Text 電子情報系シリーズ第9巻 論理回路」高木直史(著)(昭光堂) 「トランジスタ技術SPECIAL わかるVerilog HDL入門」木村真也(著)(CQ出版) |
| 自主学習ガイド及び キーワード [Self learning] |
各回の講義と教科書・参考書の対応については事前に説明するので,講義までに該当部分を予習しておくこと.また,講義中に示した演習問題を必ず復習しておくこと. |
| 開講年度 [Year of the course] |
28 |
| 備考 | 特になし |
| 資格等に関する事項 | 特になし |