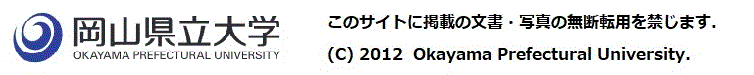
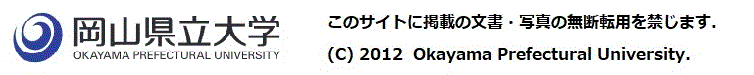
| 授業科目名(和文) [Course] |
子ども家庭支援論 |
| 授業科目名(英文) [Course] |
Support of family and Child |
| 学部(研究科) [Faculty] |
保健福祉学部 |
| 学科(専攻) [Department] |
保健福祉学科 |
| 担当教員(○:代表教員) [Principle Instructor(○) and Instructors] |
○中野 菜穂子 自室番号(5122)、電子メール(nakano**fhw.oka-pu.ac.jp) ※利用の際は,** を @に置き換えてください |
| 単位数 [Point(Credit)] |
前期 2単位 |
| 対象学生 [Eligible students] |
保健福祉学科 子ども学専攻 3年次生 |
| 授業概略と目標 [Course description and Objects] |
子どもの育ちの基盤である家庭の意義と役割を押さえ、家庭を支援する保育者が備えるべき支援の価値観と方法を学ぶ。家庭支援および機関連携について事例を基に理解する。 |
| 到達目標 [Learning Goal] |
・家庭の機能と役割をおさえ、家庭の意義について理解する。 ・子育て家庭を取り巻く現代社会の状況と支援ニーズを理解する ・家庭への支援体制と機関連携について理解する |
| 授業計画とスケジュール [Course schedule] |
第1回:はじめに 子どもと家庭 ・家庭は子どもの成育基盤である事を再確認します。 第2回:Ⅰ.家庭の意義(1)現代社会と家庭 ・家族規模の縮小、家庭機能の縮小・変化など、現代社会の変化・発展が家庭にどのような影響をもたらしたのかを各種調査を基に考えます。 第3回:Ⅰ.家庭の意義(2)家庭の重要性 ・子どもの発達・親の発達にとって家庭がどのような意義を持つのか学びます。 第4回:Ⅰ.家庭の意義(3) 家庭への支援 ・2回・3回の内容を踏まえ、現代社会において子育て家庭を支援することの必要性を学びます。 第5回:Ⅱ.支援の価値観(1)エンパワーメント ・支援者の価値観のあり方が支援の質や手法を左右することを踏まえ、支援の価値観を考えます。支援者が向き合う対象が有している可能性や力量に注目することの大切さを学びます。 第6回:Ⅱ.支援の価値観 (2) 男女共同参画 ・母親に偏在する育児負担とその背景にあるジェンダーについて学び、育児・家事における男女共同参画を考えます。 第7回:Ⅱ.支援の価値観(3)地域ネットワーク ・家庭を取り巻く地域環境について学び、子どもをはぐくみ家庭を支える地域のつながりについて考えます。 第8回:Ⅲ.家庭への支援体制(1) 家庭支援事業の概要と実際 ・子育て家庭を支える公的事業について学び、地域で支援事業に携わる専門職の講話により学びます。 第9回:Ⅲ.家庭への支援体制(2) 子育て家庭のための社会資源 ・子育て家庭が活用できる制度や機関・施設等について主要なものを解説します。 第10回:Ⅲ.家庭への支援体制(3)教育および福祉・保健・医療との連携 ・子どもの誕生と成長・学びにともなう家族の支援ニーズの変化に着目し、適切に支援または介入するために必要となる教育と福祉・保健・医療との連携及び実際のとりくみを学びます。 第11回:Ⅳ.支援の展開と機関連携(1) 幼稚園・保育所におけるとりくみ ・事例検討を通し実際の展開を学びます。 第12回:Ⅳ.支援の展開と機関連携(2)父親の育児参画支援 ・事例検討を通し実際の展開を学びます。 第13回:Ⅳ.支援の展開と機関連携(3) 地域ネットワークによる家庭支援 ・事例検討を通し実際の展開を学びます。 第14回:Ⅳ.支援の展開と機関連携(4) 保護が必要な子どもとその家庭への支援 ・事例検討を通し実際の展開を学びます。 第15回:まとめ 子育て支援の課題 |
| 成績評価方法と基準 [Grading policy (Evaluation)] |
提出物(20%)中間レポート(20%)、定期試験(60%)により評価する。欠席回数が1/3を超える場合は評価の対象としない。 |
| 教科書 [Textbook] |
教科書:使用しない |
| 自主学習ガイド及び キーワード [Self learning] |
参考書は授業の進行に伴い紹介するので、予習・復習に活用すること。 子育て支援のための制度や機関・人材などについて関心を広げること。 |
| 開講年度 [Year of the course] |
28 |
| 資格等に関する事項 | 保育士資格必修・教科または教職に関する科目(幼稚園教諭一種) |