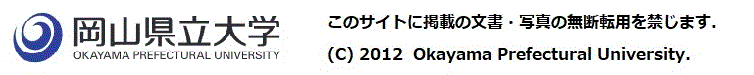
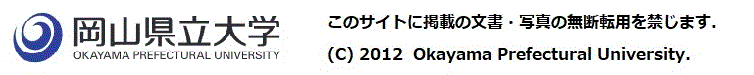
| 授業科目名(和文) [Course] |
外国文学 |
| 授業科目名(英文) [Course] |
Foreign Literature |
| 学部(研究科) [Faculty] |
共通教育/全学教育 |
| 学科(専攻) [Department] |
人文・社会科学 <人間と文化の理解> |
| 担当教員(○:代表教員) [Principle Instructor(○) and Instructors] |
○林 玉美 自室番号() |
| 単位数 [Point(Credit)] |
後期2単位 |
| 対象学生 [Eligible students] |
全学科平成26年度以前入学生(履修区分は各学科の定めによる) |
| 授業概略と目標 [Course description and Objects] |
20世紀初頭のイギリスの作家、E・M・フォースター(1879年~1970年)の作品、特に「インドへの道」(A Passage to India)を通して、作家の精神世界を理解する。同時に、作品を通して、当時、世界最大の覇権を握っていたイギリスの地位の揺らぎとそれに伴うイギリス文化の伝統的性格の変容とインド文化の多様性と寛容を探究する。 |
| 到達目標 [Learning Goal] |
1.異質な価値観を有する者同士が接触することから生じる動揺の種々相を理解する。 2.文学作品を通して、「他者」の文化に関連する諸事について深く理解する。 3.自国の文化および「他者」の文化の種々相を複眼的な視点から捉えることができる。 4.クリティカル・スィンキングの萌芽となる,「比較」という学究的な態度を錬磨する。 |
| 履修上の注意 [Notes] |
*ハンドアウトを読んでおき、テーマについて自分で調べておく。 *各講義のテーマに即した課題の提出が必須である。 *作品の理解のために、映像資料を用いる。 *補助資料として,英語の文献を用いることがあるが、翻訳作品は必ず読むこと。 |
| 授業計画とスケジュール [Course schedule] |
1. 序論①:E・M・フォースターの経歴と作品の紹介 2. 序論②:イギリスの知的精神についてー「ブルムズベリーグループ」の影響 3. 作品の背景①:大英帝国、イギリスの文化的種々相、植民地における文化的優位について 4. 作品の背景②:キリスト教・イスラム教・ヒンドゥ教の比較 5. 作品の背景③:インド社会における民族や文化の多様性 6. 作品の理解①:「インドへの道」を鑑賞 7. 作品の理解②:主要な登場人物、アジズ医師・モア夫人・アデラ・ゴドボレ教授の心の動きについて感想を発表 8. 作品の諸相を探索①:「モスク」異文化との出会いと動揺 9. 作品の諸相を探索②:「モスク」多文化共存社会における対立と寛容 10.作品の諸相を探索③ :「洞窟」異文化への探求がもたらす衝撃 11. 作品の諸相を探索④ :「洞窟」異文化の衝突、民族意識の高揚 12. 作品の諸相を探索⑤ :「寺院」異文化の共存と相反 13. 作品の総括①:「インドへの道」にみる異質な価値観への心的態度 14. 作品の総括②:E・M・フォースターの精神世界の葛藤と知的寛容性 15. 異文化受容の諸相を探究 :グループによる発表 |
| 成績評価方法と基準 [Grading policy (Evaluation)] |
授業内課題(発表を含む)40% 授業外課題(課題のテーマについて、小論文を提出)40% 授業への積極的参加 20% を配点として総合的に評価する。 |
| 教科書 [Textbook] |
毎回、担当教師がハンドアウトを用意する。 |
| 自主学習ガイド及び キーワード [Self learning] |
授業中に、参考図書等を紹介する。 予習として、作品の指定範囲を読んでおき、出来事と人間関係を整理しておくこと。 |
| 開講年度 [Year of the course] |
28 |
| 備考 | 授業中に、担当教師へのアクセス方法を通知する。 |