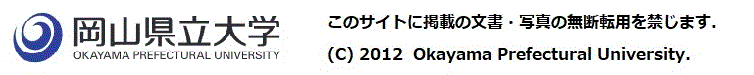
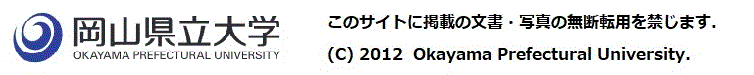
| 授業科目名(和文) [Course] |
運動機能工学 |
| 授業科目名(英文) [Course] |
Engineering of Motor Function |
| 学部(研究科) [Faculty] |
情報系工学研究科 |
| 学科(専攻) [Department] |
システム工学専攻前期 |
| 担当教員(○:代表教員) [Principle Instructor(○) and Instructors] |
○髙戸 仁郎 自室番号(5114)、電子メール(takato**ss.oka-pu.ac.jp) ※利用の際は,** を @に置き換えてください |
| 単位数 [Point(Credit)] |
後期 2単位 |
| 対象学生 [Eligible students] |
1・2年次生 |
| 授業概略と目標 [Course description and Objects] |
人の機能や動的特性を理解し、人を中心とした機器、システムの開発ができるようになるための方法を身につける。 |
| 到達目標 [Learning Goal] |
1)人の運動器の構造と機能を理解する。 2)人の動作特性を解析する視点や技術を理解する。 3)人の動作特性を考慮した機器やシステムの適合について理解する。 |
| 授業計画とスケジュール [Course schedule] |
1.オリエンテーション 2.肩の運動特性 肩の機能と構造について理解し,運動障害の発生機序と予防法について考える. 3.肘の運動特性 肘の機能と構造について理解し,運動障害の発生機序と予防法について考える. 4.膝の運動特性 膝の機能と構造について理解し,運動障害の発生機序と予防法について考える. 5.股の運動特性 股の機能と構造について理解し,運動障害の発生機序と予防法について考える. 6.足の運動特性 足の機能と構造について理解し,運動障害の発生機序と予防法について考える. 7.手の運動特性 手の機能と構造について理解し,運動障害の発生機序と予防法について考える. 8.運動機能の計測法 加速度計,床反力計など様々な運動計測装置を用いた計測法について理解する. 9.感覚器と運動 感覚器の機能と構造について理解し,感覚機能と運動の関係について考える. 10.感覚代行支援機器 感覚機能が障害された際に活用される感覚代行支援機器について理解する. 11.感覚代行機器開発の視点 感覚代行機器の抱える問題点について理解し,新たに開発する際の留意点について考える. 12.運動機能障害の特性 運動器の機能障害について,その発生機序を理解する. 13.運動機能障害の代行 運動器の機能障害を代行する手法,支援機器について理解する. 14.運動支援機器の開発 運動機能が障害された人に対する支援機器の種類を理解し,新たに開発する際の留意点について考える. 15.運動支援機器の実際 運動機能が障害された人に対する支援機器の機能を評価する手法を理解し,新たに開発する際の留意点について考える. |
| 成績評価方法と基準 [Grading policy (Evaluation)] |
到達目標の達成度を,学習態度(30%)と提出課題(70%)により評価する. 筆記試験は授業の進行度合いに従って別途実施する. なお,提出物については日本語または英語による. |
| 教科書 [Textbook] |
使用しない. |
| 自主学習ガイド及び キーワード [Self learning] |
授業終了時に次回の授業のポイントを指示するので、参考書に目を通すこと. |
| 開講年度 [Year of the course] |
28 |